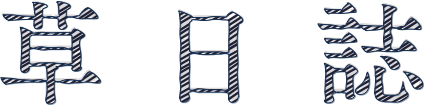2025年9月25日
第33回 映画とごはんの会
『竹縄のさと』

民族文化映像研究所作品の上映会 33回目「映画とごはんの会」のプログラムが決まりました。
10月は東秩父の『竹縄のさと』を上映します。
竹縄は丈夫で弾力性にとみ、また水に強い。東秩父村で作られた竹縄は、東北地方南部一帯から関東地方一円にかけて用いられてきた。竹縄にはマダケとハチクを用いる。萩平の人々は、米のとぎ汁や煮た大豆をまいて竹林を大切に育ててきた。
秩父は山国でその山ひだの奥に、静かなそしてひたむきな人のくらしがある。埼玉県秩父村その外秩父の奥にある萩平、ここではその年生えた若竹で縄をつくる技術が伝えられている。伝承者であるすでに80歳を越えた老人2人と、それを助ける人たちによって1978年夏から秋にかけて行われた竹縄づくりとその多彩な利用の記録です。
36分の作品です。
予告編は 【こちら】 からご覧いただけます。
お待ちしています。
【会場】信陽堂アトリエ(文京区千駄木3-51-10-1F)
【日時】
2025年10月24日(金)
〈夜の部〉 満席となりました
19時上映開始(開場は18時30分)22時終了
参加費 4000円(ワンドリンクと酒肴つき 税込)
定員 10名
2025年10月25日(土)
〈昼の部〉 【予約する】
15時上映開始(開場14時30分)17時終了
参加費 2000円(お茶とお菓子付き 税込)
定員 10名
〈夜の部〉 満席となりました
19時上映開始(開場は18時30分)22時終了
参加費 4000円(ワンドリンクと酒肴つき 税込)
定員 10名
上の「予約する」からフォームに入れない場合、
あるいはキャンセル待ちをご希望の方は【ここをクリック】
「お問い合わせ内容」に「竹縄 参加希望」「キャンセル待ち希望」
〈希望日〉と〈昼の部〉か〈夜の部〉か、当日連絡が取れる電話番号、複数でお申し込みの場合は人数もご記入ください。
また、食品アレルギーがある方は、その旨もご記入ください(お食事、お菓子の参考にいたします)。
*感染症対策として、手指消毒用のアルコール、ジェルをご用意します。
当日体調の優れない方の来場はご遠慮ください。
せき、くしゃみなどの症状がある方は入場をご遠慮いただきますのでご了承ください。
状況によっては、上映中はマスクを着用していただく場合がございます。


「映画とごはんの会」は
作品の上映と、そのあと1杯のお酒とおつまみをご用意した会です。
1)自己紹介は必要ありません
2)感想も求めません
とはいえ、映画を観たあとには浮かび上がるいろいろな思い、疑問があると思います。
ゲストに、民映研の創立メンバーでこの映画の撮影も担当した伊藤碩男カメラマンと、民映研の代表の箒有寛さん(ShuHALLI)をお迎えします。
湧きあがる疑問には、博覧強記の伊藤さんと箒さんが驚異の記憶力をもって答えてくださるはずです。
お弁当は「たまや」が担当します。
おいしいお酒と肴とおしゃべりを楽しみましょう。

『竹縄のさと』
1979年/36分/自主制作/埼玉県秩父郡東秩父村御堂荻平/文部省選定
【作品解説】
東秩父村は秩父山地の東側にある集落で、昭和20年代まで盛んに竹縄が作られていた。その経験者、関根ヒロさんと若林チョウさんを中心に、萩平の人々によって行われた竹縄作りと、その多様な利用法の記録である。
竹縄は丈夫で弾力性にとみ、また水に強い。東秩父村で作られた竹縄は、東北地方南部一帯から関東地方一円にかけて用いられてきた。竹縄にはマダケとハチクを用いる。萩平の人々は、米のとぎ汁や煮た大豆をまいて竹林を大切に育ててきた。竹伐り旬(最も適した竹が得られる期間)は、7月末から8月初めに3日間ほどしかない。この間に新子(その年に生えた竹)を伐り、火にあぶって油抜きをし、細く小割りにする。そして乾かして、秋まで火棚の上や屋根裏に保存する。
縄にする作業は秋から翌年春までの農閑期に行う。沢の水をせきとめて作った竹シテ場に、小割りした竹を1週間漬けて柔らかくする。
柔らかくなった竹の表皮を剥ぐ。次に「竹ヘギ」、肉質部を0.5ミリぐらいに薄く剥ぐ。肉の厚い竹で12枚、薄いもので6枚くらいに剥ぐ。「縄縒り」、縒りをかけながら長くつないでいく。縒った縄はクモデに巻きとる。「縄ブチ」、クモデを使って縒った縄をさらに3本縒りにする。そして、縒りかけ機で縒りをしめ、「コスリ」をして縄目をつぶす。
竹縄には、その特徴を生かしてさまざまな利用法があった。屋根材や蚕棚の結束、井戸の釣瓶縄、足洗い下駄の鼻緒、自在鉤の結束、牛馬のくつわ、まつりの山車の土台の結束などである。また秩父地方では、死者の棺をになうとき、必ず竹縄を1本使わなければならないとされていた。
秩父の山村の人々にとって、竹縄は日常生活になくてはならないものであると同時に、生活の糧を得る重要な手段でもあった。
©民族文化映像研究所/『民映研作品総覧』(はる書房)より転載
最新記事
- 柳亭市若さん
如月の落語会
「看板のピン」2026年02月07日 - 松井至『つぎの民話』
刊行記念 上映+トーク
〈名前のないものを共に見る〉
@ Readin’ Writin’ BOOK STORE2026年01月28日 - ソラノマド|高山なおみ
ラジオの声2026年01月27日 - 映画とごはんの会〈アンコール〉#01
『武州藍』2026年01月22日 - 第35回 映画とごはんの会
『旧原家住宅の復原』2026年01月22日
アーカイブ
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年4月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年6月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年2月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2015年9月
- 2015年4月
- 2015年2月
- 2014年11月
- 2014年9月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2013年8月
- 2013年6月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月