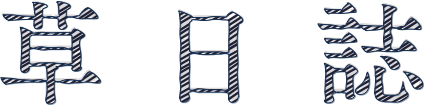2025年10月6日
ソラノマド|高山なおみ
遠い音、近い音

| 遠い音、近い音 |
窓辺でヨーグルトを食べる朝の時間、海の端が光るようになってきた。夏の間じゅう隣の建物に隠れていた陽の出が、海にだんだん近づいたせいだ。
空が赤く染まりはじめるのは、5時半くらい。そのうちに薄明るくなり、赤や黄や銀色のビーズみたいに光っていた街の灯りもほとんど消える。
陽の出を迎えると、どこからか小鳥たちの声が聞こえてくる。
遠くを走りぬける電車の音、西の海から帰ってきたフェリーが、港に着く前に鳴らす汽笛。
少しずつ、少しずつ、朝の音が目を覚ます。
いつだったか、このぐらいの時間にカラスが1羽電線にとまってこちらを伺っていた。カラスって、あんなに真っ黒でつやつやとしていたっけ。頭も大きいし、胴体ごと振り返る感じが人に似ているな、などと思いながら見ていたら、ぴしゃっと大きな音がして、白いフンが道路に落ちた。
朝は、そのくらい静か。
昼は昼で、雑音混じりのラジオの音楽と、小鳥たちのさえずり、たまに教会の鐘が鳴るくらい。ときおり車の止まる音が聞こえると、窓に確かめにいく。何が起こるわけでもない。宅配便か、郵便屋さんの赤いバイクが、荷物や手紙を届けにきたのだ。
そんな、遠くからやってくる音ばかりを聞きながら暮らしているせいか、たまに電話がかかってくると、人の声がとても近くに感じる。
窓辺のテーブルにスマートフォンを置き、スピーカーモードにして話すのだけど、この間、いちども会ったことのない方と仕事の話をしていたときには、とくに近くに感じた。
私は声に集中しながら、まるで彼女が目の前にいるみたいにイメージをしたのだと思う。
声には、たくさんの情報が詰まっているから。
東京にいたころ、はじめての方から仕事の依頼をいただくと、まず電話をもらい、声を聞いてお受けするかどうかを決めていた。
神戸に越してきてからなのか、コロナのころからなのか、ちかごろは電話どころか、顔をつき合わせながらの打ち合わせも滅多にしなくなった。
原稿の依頼を受けたり、書いたものを締め切りまでにお送りするだけなら、メールの文面だけでも充分なのだけど。いつも、なんとなしに物足りないような、目に見えないところに小さな忘れものをしているような気持ちになる。
子どものころ、いや、二十代、三十代になっても、私は電話が苦手で、自分からかけられなかった。吃音のせいで、話そう、話そうとするとプレッシャーに押しつぶされ、声が出なくなる。
それでも、どうしてもかけなければならない用事のときには、勇気をふりしぼってダイヤルをまわした。
るるるるる るるるるる と、呼び出し音が鳴っている間、心臓はばくばく。受話器から、自分の鼓動が聞こえてきそう。
そして開口一番、相手の「もしもし」に少しでも投げやりな音声や、苛立ちの欠片が混ざっていると、瞬時に反応し、声が出なくなった。
今は、明るい声でどこへでも電話をかけられるけれど、こうなったのはつい最近。神戸でひとり暮らしをするようになって、必要に迫られたからだと思う。
どきどきしながら、電話の声に耳を澄まし、相手のことを想像するのは、なかなかありがたい時間かもしれない。
声や息遣い、ときおり挟まれる沈黙は、言葉よりもずっと正直だから。
〈 了 〉

文・写真 高山なおみ
最新記事
- 丙午 2026年
今年もよろしくお願いいたします2026年01月01日 - ソラノマド|高山なおみ
踊り場の小窓にて2025年12月25日 - 柳亭市若さん
師走の落語会
「掛け取り〜2025有馬記念〜」2025年12月08日 - 第34回 映画とごはんの会
伊藤碩男翁追悼
『山に生きるまつり』2025年11月20日 - ソラノマド|高山なおみ
ぼくらは森へかえることにした2025年11月14日
アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年4月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年6月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年2月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2015年9月
- 2015年4月
- 2015年2月
- 2014年11月
- 2014年9月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2013年8月
- 2013年6月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月