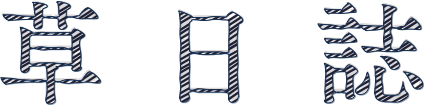2025年11月3日
ソラノマド|高山なおみ
栗の渋皮煮と『リトル・フォレスト』

| 栗の渋皮煮と『リトル・フォレスト』 |
雨がそぼ降る肌寒い日に、秋の詰め合わせが届いた。兵庫のちょうどまん中辺り、山と川と田んぼに囲まれたところで食堂をやっている、律ちゃんと靖さんからだ。
まっ白な新米は、この秋からお店でも出すようになった近所の農家の。隣のおじさんからいただいた、柚子とスダチのお裾分け。そして、丹波の大きな栗。季節の贈りものは、贈る人の近くにあるものほどうれしく、胸があたたかくなる。
そういえば、6月に綴った「梅雨の晴れ間のお便り」に添えた写真も、ふたりの庭で採れた梅の実だ。あの日は夏至の前日で、蒸し暑かったけれど、箱を開けたとたんに私は甘酸っぱい匂いに包まれた。ざるに並べ、風通しのいい窓辺に置いた。夕方の光を受けた黄梅と海の青のコントラストがきれいで、思わず写真を撮ったのだ。
栗の季節は短い。東京にいたころの私は、栗の実が八百屋さんに並びはじめるとそわそわし、夫のために栗ご飯を炊いた。むいた栗を網の上で転がし、焼き目をつけてから炊いた栗ご飯も香ばしかったし、食後の甘味を楽しみにしている彼のために、渋皮煮も何度かこしらえた。
ひとりになってからは、簡単にできる栗ジャム(鬼皮ごとゆでたらスプーンで実をかき出し、お砂糖と合わせて煮るだけ)ばかり。それでも手のひらに乗るくらいとっておいて、お米1合で栗ご飯を炊き、秋を楽しんだ。
今年は、同じマンションの文子さんから、お手製の渋皮煮をいただいた。それですっかり満足してしまい、栗ジャムも栗ご飯も炊かなかったのだけれど、こんなに立派な丹波栗をいただいたのだから、久しぶりに渋皮煮をこしらえようと思い立った。
私の渋皮煮の先生は、映画『リトル・フォレスト 夏/秋』の主人公、いち子ちゃん。
座卓に新聞紙を広げ、DVDを見ながら鬼皮をむきはじめる。映画の中と同じ寒さに身を置きたくなり、ココアをいれた。とちゅうで扇風機もしまい、電気ストーブを出した。
いち子ちゃんのナレーションは、詩のように歯切れがいい。そして、ワンシーンごとがそのまま、分かりやすいレシピになっている。
栗拾いはクマに注意。長靴と炭バサミで、イガから取り出す。
硬くなるので早めに鬼皮をむく。
古い栗は、軽くゆでるとむきやすい。
灰か重曹を入れた水にひと晩浸けておく。
次の日、そのまま火にかけ、弱火で30分煮る。
煮汁はアクでまっ黒。水を替え30分煮る。また水を替え、30分。
これを繰り返していくと、煮汁が澄んだワイン色になってくる。
とちゅう、スジとワタを取ってきれいにそうじ。
煮上がった栗の重さの60パーセントの砂糖で煮詰めていく。
火を止める直前に、酒類で香りをつけてもおいしい。
保存する場合は汁ごとビンに入れる。
煮汁のまま2、3ヶ月おくと、しっかり糖が染み込んで、ねっとり。
私はこの方が好き。渋皮のところが、まるで餅菓子みたいな食感だ。
ところが私は映画に夢中なあまり、肝心な渋皮を包丁の先でいくつも傷つけてしまった。ちょっとでも穴が空いたら、ゆでこぼしている間に割れてしまうから、渋皮煮には使えない。
穴の空いた栗は、すっかり渋皮をむきとり、スープにすることにした。鶏肉でもあればよかったのだけれど、冷蔵庫にはキャベツと玉ねぎしかない。
まず、鍋でバター10グラムを溶かす。玉ねぎ1/2個は半分にして、切り口をバターで焼きつけ、焼き目をしっかりつけてから、栗の実を5、6粒加える。
栗にもバターをからめ、芯をつけたまま4センチ幅の扇型に切ったキャベツを2切れ、玉ねぎと栗の上にかぶせる。お酒を少し、水も少なめ。ローリエ1枚と塩ふたつまみを加えてふたをし、弱火でコトコト。
バターとローリエの威力はすごい。これだけで、スープの素を入れたみたいな洋風の香りが台所に漂い、玉ねぎと栗の甘みのとてもおいしいスープができた。
あと片づけをしながら、渋皮がきれいに残った栗だけを鍋に入れ、重曹入りの水に浸けた。
まっ暗な台所で、ひっそりと、映画みたいにこのままひと晩浸けたら、明日の朝、ゆでこぼす予定。
東京にいたころにも、『リトル・フォレスト』を見ながら渋皮煮をこしらえたことを、日記に書いたような気がして、自分の本(『帰ってきた 日々ごはん④』)をめくってみた。
日づけを確かめると、2015年の9月22日。
『リトル・フォレスト』を見るのも、渋皮煮をこしらえるのも、10年ぶりのことだった。
10年なんてあっという間。
あのころから私は、何が変わって、何が変わらないんだろう。
〈 了 〉


文・写真 高山なおみ
最新記事
- 松井至『つぎの民話』
刊行記念 上映+トーク
〈名前のないものを共に見る〉
@ Readin’ Writin’ BOOK STORE2026年01月28日 - ソラノマド|高山なおみ
ラジオの声2026年01月27日 - 映画とごはんの会〈アンコール〉#01
『武州藍』2026年01月22日 - 第35回 映画とごはんの会
『旧原家住宅の復原』2026年01月22日 - 丙午 2026年
今年もよろしくお願いいたします2026年01月01日
アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年4月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年6月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年2月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2015年9月
- 2015年4月
- 2015年2月
- 2014年11月
- 2014年9月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2013年8月
- 2013年6月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月