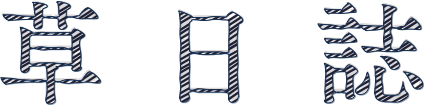2025年10月6日
『つぎの民話』試し読み
握手|プロローグ
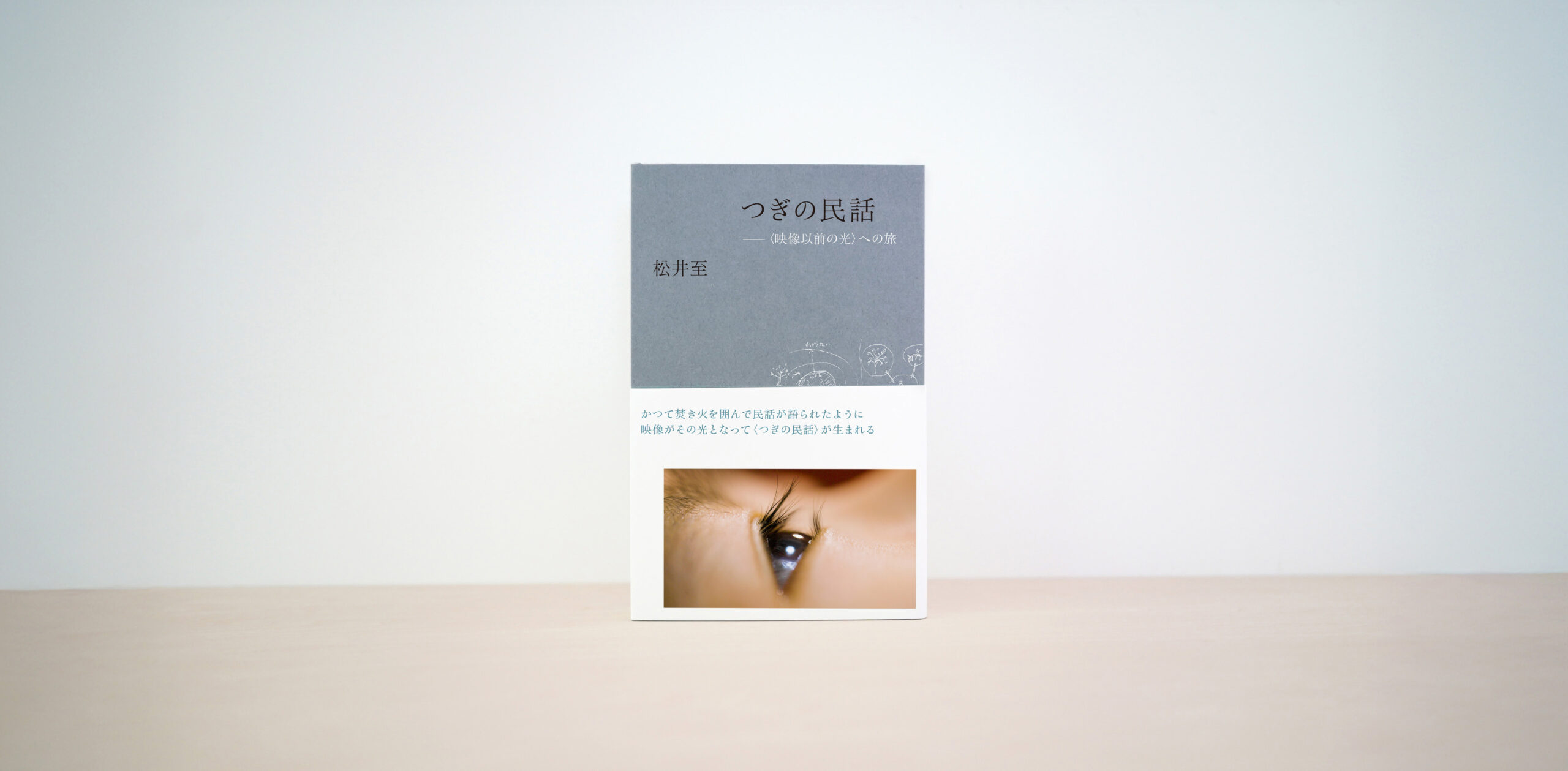
[松井至『つぎの民話』より「握手|プロローグ」を無料公開しています。
書籍版は【こちら】から購入いただけます]
十代の終わり頃だった。
ひとり暮らしのアパートで宅配便の再配達を頼もうとダイヤルを押した携帯から配達員の声が聞こえたとき、自分の名前をすっかり忘れていることに気がついた。
お名前は?
そう二度三度くりかえすこととなった配達員の舌打ちが聞こえてきそうで、咄嗟に机の上の郵便物をかき分けて宛名欄を読み上げる。その口のなめらかな動き。自分はこの名前を何千何万回も口にしてきた。こんなあたりまえのことを考えたのは生まれてはじめてだ。汗が噴き出し、眩暈がする。その日は気絶するまでアルコールを吞んだ。自分の名前すら忘れる人間に未来があるとは思えなかった。最悪なことにそれからも似たようなことが大小無数に起きた。これからも起こるにちがいない。
ぼくはそんなふうにできている。
これまでの人生についてほとんど覚えていないし、思い出したいとも思わない。
十数年間を刑務所で過ごした友人と歌舞伎町で朝まで吞んだことがあった。
目が覚めるたびに自由を感じる
と彼は言った。目を覚ますたびに刑務所備え付けの剝き出しの蛍光灯の光を見る生活が終わったのだ。
毎朝、起きて、あの蛍光灯の光を見て、決められた廊下を歩いて、曲がって、決められた飯を食って、クソして、寝る。また朝が来て、あの光を見る。それだけを十数年していたら、自分の記憶とか過去とか、そういうのは俺が勝手に妄想しているだけでね、刑務所で生まれ育ったという方がリアリティーを持ってくるのね。だって自分が生きてきたってことを知っている人がいないわけだから。確かめられない。周りの人が外部記憶装置みたいになって、そこに自分が生きていた記憶が残ってるから。ずっとひとりでいると自分のことすら覚えていられない。「噓じゃないか」と思うわけ。
身振り手振りをまじえて出所当時を振り返る。
いま目の前に見えている皿とか肉とか酒とかスマホとか、中にはなかったから。刑務所にないものは現実味がないと感じる。触ったら本当に在るのかな? VRみたい。出所祝いで食べ物屋に連れていってもらって。ありがたいんだけど「何がいい?」って聞かれても答えられない。「選ぶ」なんてずっとしてないから。うどんの種類を選ぶだけで、ものすごくくたびれる。
ある日、彼は出所前からの知人と再会し、映像を見せられた。
中学くらいの頃にテレビ局がニュースの撮影に来て、俺らがつるんでいるところを撮っていったときの映像があって。けっこう有名な不良だったから。それでガキの頃の俺がインタビューされてて。食事を前にして「なぜ飯食うのに順番があるんだ? デザートから食って何が悪い?」って話をしていて。決められたルールに従いたくなかったわけ。「ああ、こいつ、いいこと言ってるじゃん」って。「自分はたしかにこんなふうに生きてた」って思ったんだよね。映像が俺を覚えていてくれた。そんとき思い出せた。俺には俺の人生が在ったんだって。
ふと体が過去のワンシーンに揺り戻されることがある。
きっかけは些細なことだ。シャワーを浴びるとか、子どもと頰を重ねるとか。旬の食べものを口に入れる。宙に舞う埃を眺める。波の音。草いきれ。焚き火の熱。誰かの語りの声に溶けていくとき、ある固有の時間がありありと甦る。陽射しに全身を焼かれた海岸が甦り、雪に埋もれて身動きがとれなくなった山が甦り、迷子になって泣きながら歩いた人混みが甦り、いつからか背中に置かれていた誰かの手に安堵して眠りに落ちる感覚が甦る。
皮膚はこれまで通り過ぎてきた情景を焼き付けて内蔵しているのではないか。
皮膚の下に〈ここではないどこか〉が波打っていて、外からの刺激をきっかけに過去のワンシーンへと意識を放り込むのだ。それが自分の記憶なのか他者の記憶なのか、実際に見たのか脳が作り出すのか、わからない。
ある固有の時間がまざまざと甦り、ひとりでは思い出せなかった自分を思い出す。
それが自分なのかどうかもわからない、自分以前を思い出す。
映像はもともと皮膚だったのかもしれない。
はじめて訪れる土地ではスマホを切って迷子になる。
ふと自分はここに生まれ育って、あの角を曲がってすぐのカフェにいる友人に会いにいくところだと考えてみる。あるいは仕事帰りの会社員で家族のための献立を考えつつスーパーへと急いでいる。たまたまそうでなかっただけだ。たまたまここではない場所に生まれて、たまたま今日、撮影をするためにこの近くに泊まり、たまたまこの通りを歩いている。もうそんなことはどうだっていい。ほんのわずかな差で、ぼくは他人だった。迷子になって、その路地の人物になってみる。たったいまはじめて目にする光景が懐かしい。
いまならこの土地が写る気がする。
子どもの頃から言葉が嫌いだった。
目の前に花が在るのに「綺麗だね」という一言で花が枯れる気がした。皆で笑っていたのに「幸せだね」という一言で噓になる気がした。
言葉が世界にしうる収奪は凄まじかった。
あらゆる事物から名前を剝ぎとってしまいたかった。コップがコップではなく、水が水ではなく、手が手ではなかったら。わたしがわたしでなく、あなたがあなたでなかったら。なにも分別されておらず、どこまでも差異が広がっていて、二度と繰り返すことのないこの世界を指差すことは誰にもできない。
最初の記憶はなんだったか覚えてる?
親戚との花見の席で、叔父が声をかけてきた。
俺はね。母親の背中におんぶされて、手足を目一杯動かした感触が残ってる。
酒飲みの家系だからいつも大声が飛び交っていて、それが疎ましくなる年頃だったので、人の輪からはぐれた感じのする叔父との会話は心地よかった。それから自分の記憶を探ってみた。
見渡す限りの荒野に一本道。そこに一頭の馬が立っていた。
あれは数秒か、十数秒だったのか、子どもの目には途方もなく長い間、その馬が震えながらかろうじて立っているように見えた。
突然、前触れもなく馬は崩れるように倒れる。
記憶のはじまりに奇妙な白黒のフィルムが焼き付いているのを見つけた。数年後、映画についての本を読んでいて「病馬が倒れる」という一節に会い、それが『戦ふ兵隊』(一九三九年製作、亀井文夫監督)だと分かった。戦意高揚のため、陸軍の支援を受けて日中戦争に従軍しながら作られたが、反戦芸術と判断され公開禁止となった幻の映画だった。
祖父がこれを観させた。
なぜ馬は死んだの?
と尋ねた気がする。
彼はなにか答えたはずだが、その口元の微笑み以外なにも思い出せない。
祖父は別れるときに必ず握手をする人だった。
もし彼の温厚なひととなりを知らなかったら咄嗟に振りほどいてしまうほどに、思い切り掌を握りしめる握手だった。
誰に対してもそうしていたらしい。
別れてからしばらくは手が痺れた。それが不思議と爽快ですらあった。
あの握手には悪意がまったくなかった。
生きてまた会えると信じる純真と、明日死ぬことが決まっているかのような「さようなら」が目一杯つまっていた。
ぼくは密かにそれを戦争の痕跡だと考えていた。
映画の上映後に声をかけてくれる人がいる。
堰を切ったように自分の話をしていく。
子どもの頃、親の都合でアメリカの田舎に引っ越して、日本人が誰もいない地域で。不安で喋れなくなってしまったんです。それを見かねた牧師さんが自分と同じような移民の子に会わせてくれて。救われたんです。いまでも連絡をとっているんですよ! あの時期に打ち解けられる仲間がいなかったら死んでたなって。ごめんなさい。なんか自分の話ばっかりで。映画を観ながらずっと思い出していました。
隣でパートナーの方が「はじめて聞いた」とつぶやく。ひとつの映画の光を観ながら、同時にもうひとつの映画のようなものが個々人の内で上映されている。
映画館の出入口に立って、これから暗闇の中で他者の生に触れようとする人たちを見送る。映画がはじまると最初の数分は知り合いのいないパーティーに来たように馴染めない。
ここにいていいのかを考えてしまう。
それから自分自身に許可を求める。
映画に映る他者を感じていいのか。
ともに笑っていいのか。
泣いていいのか。
愛おしくなっていいのか。
美しいと思っていいのか。
怒っていいのか。
安堵していいのか。
あかの他人ではなく、親密な人として受け入れていいのか。
その許可をおろす。
うまくいけばなにかを思い出すかもしれない。いや「うまくいけば」という言い方はおかしい。思い出したくないことを思い出してしまわないように、映画館に来ない人は多い。
映画の半分は観る人が作る。
複製芸術である映画は上映の真っ只中にその光を観る個々人に委ねられ、その心の内で固有の経験へと変容している。
そうでなければ何時間も黙って他者の生に触れる必然がない。
あなたはあなたであり、わたしはわたしであるという分別を完結できるならドキュメンタリーなどこの世になくても済むが、人はそんなふうにできていない。
空の見方を教えてくれたのは祖父だった。
小学三年生の夏休み。釣りのことで頭をいっぱいにしていたぼくは、明け方に目覚ましをかけ、祖父を起こし、釣具を持って防波堤へと歩く。昨晩、遅くまで研究した仕掛けに餌をつけ、海に垂らす。じっとウキを見る。見続けていれば釣れると信じていた。
おおい こっちに来て寝転がれよ
振り向くと祖父はアスファルトに大の字に寝転がっている。渋々、祖父の隣に寝転がりながら釣り竿を見る。魚が餌をつついているのか、竿の先がぴくぴくと揺れる。引き揚げなければ、と立ち上がる。
餌はぜんぶ魚にやれよ
祖父は他人が何かしようとしているときに割って入るような人ではなかった。よほどのことだ。今日はもう諦めて言うことを聞こうと考え、餌をぜんぶ海に投げてもう一度寝転がる。
空を見てみろよ
宙空に向いた彼の瞳が真横にあった。
その瞳は近くにあるのに、はるか彼方にあるようだった。脚本家だった彼は原稿を綴るとき、青いインクで出来たひとつひとつの文字を、まるで宝石の輝きを確かめるように眺めていた。そうして世界を形作る言葉の響きに目をこらすことで、祖父は奇跡的に幼年期の瞳の輝きを保つことに成功していた。
なにか見せたいものがあるのか。それともなにか面白い話でもあるのだろうか。そんな期待が消えてなくなるほど長い沈黙の中、アスファルトに自重を預けて見上げる空をトンビが横切る。
どれくらいそうしていただろう。
空を見ているうちに空そのものになってしまった。
肉体が気体になって、大きな空のすみずみまで音もなく広がる。はじめは所在がなくなるようで怖かったが、空間に無限に溶け出していく感覚にすっかり没入した。いつしかふたりとも眠りに落ちていた。
帰路についても空になった感覚が体を占領していて、何度も転びかけた。
空を見るのではなく、空になるのだ。
なにも持たずに。
祖父はそうやってぼくに生きることを教えた。
十四歳のときに祖父は死んだ。
癌が転移して苦痛に苛まれているはずなのに彼は自分の体を他人事のように捉えていて、痛みを口にしなかった。死期が近いので、病室のベッドの横に布団を敷いて泊まった。彼の友人たちが次々と見舞いに来て、ぼくの顔を眺め「お孫さんかい?」と尋ねる。その度に、彼はかすれた声を搾り出して「そんなもんじゃないんだ」「俺の親友なんだ」と言った。
医師にモルヒネを使うかどうかを問われて、祖母がそれに同意し、祖父はほとんど動かなくなった。ただ呼吸する胸だけを上下させて、瞳は宙空を見つめていた。
人の死に立ち会うのは、はじめてだった。
モルヒネで意識を失った祖父の手を握ったまま眠り、起きても握り続けて三日ほど過ごした。骨の浮き出たその体を覆っているなめらかな皮膚は、いつもより白くほのかに明るかった。すべての役目を終えた肉体から生気がなくなるのを見届けていた。親友の最期をなにもかも覚えておかなくてはならないと思い込んでいた。
突然、意識のないはずの祖父の手が、ぼくの手を握り返す。
掌が潰れるほど、強く。
別れるときに必ず握手をする人だった。
数時間後に心拍が停止した。彼の顔に不似合いな化粧が施され、葬式がはじまり、火葬が終わってもぼくはずっと驚き続けていた。あの握手は死の方からやってきて語りかけたのだ。百万語を費やすよりはるかに饒舌に。それを読み解くことがそのまま生きることになるように。これまで認識していた世界は実は半分で、もう半分、死の世界があると知った。
祖父はそうやってぼくに死を教えた。
私が消えて、人と人とが直通になる瞬間があるんです
つい先日、手話通訳士の方をインタビューしたらそんなふうにおっしゃった。ろう者と聴者、聴こえない世界と聴こえる世界を行き来して、心の壁をなくそうとする冒険の楽しさが伝わってきた。
制作も同じだ。
映像を媒介に人と人だけでなく、人と死者、人と他の生きもの、人と物、人をとりまくあらゆる存在との間を行き来する〈存在の通訳〉になれたらと思う。通訳が成立すれば自分が消えて、人と世界は直通になる。
撮影現場に着く。
出演者をとりまく空間に入る。
目が合って挨拶を交わすまでのわずかな間に、ここでこれから撮るショットや音の響き、存在の表情が洪水のようにやってくる。
「はじめまして」の裏で「ようやく会えた」と感じる。
「よろしくお願いします」の裏で「さようなら」を覚悟する。
ここで起こるあらゆる情景を焼き付ける。
現場ではなにもかも覚えておかなくてはならない。
「ありがとうございました」と立ち去って、ふと考える。
映像は握手にならないか。
思い切り掌を握りしめて、生きることに迷ったらいつでもそこに帰ってこられる魂の故郷のような握手にならないだろうか。
〈握手|プロローグ 了〉
松井至[まついいたる]
1984年生まれ。人と世界と映像の関係を模索している。
耳の聴こえない親を持つ、聴こえる子どもたちが音のない世界と聴こえる世界のあいだで居場所を探す映画『私だけ聴こえる』が公開され、海外の映画祭や全国40館のミニシアターで上映され反響を呼んだ。令和4年度文化庁映画賞文化記録映画大賞受賞。
誰からでも依頼を受けるドキュメンタリーの個人商店〈いまを覚える〉を開店。
日本各地の職人と自然との交わりをアニミズム的に描いた〈職人シリーズ〉を展開。
コロナ禍をきっかけに、行動を促すメディア〈ドキュミーム〉を立ち上げる。
無名の人たちが知られざる物語を語る映像祭〈ドキュメメント〉を主催。
仕事の依頼などは 【こちら】まで。
最新記事
- ソラノマド|高山なおみ
雪の日2026年02月18日 - 柳亭市若さん
如月の落語会
「看板のピン」2026年02月07日 - 松井至『つぎの民話』
刊行記念 上映+トーク
〈名前のないものを共に見る〉
@ Readin’ Writin’ BOOK STORE2026年01月28日 - ソラノマド|高山なおみ
ラジオの声2026年01月27日 - 映画とごはんの会〈アンコール〉#01
『武州藍』2026年01月22日
アーカイブ
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年4月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年6月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年2月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2015年9月
- 2015年4月
- 2015年2月
- 2014年11月
- 2014年9月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2013年8月
- 2013年6月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月