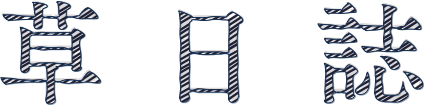2025年10月6日
『つぎの民話』試し読み
光を読む|映画『私だけ聴こえる』
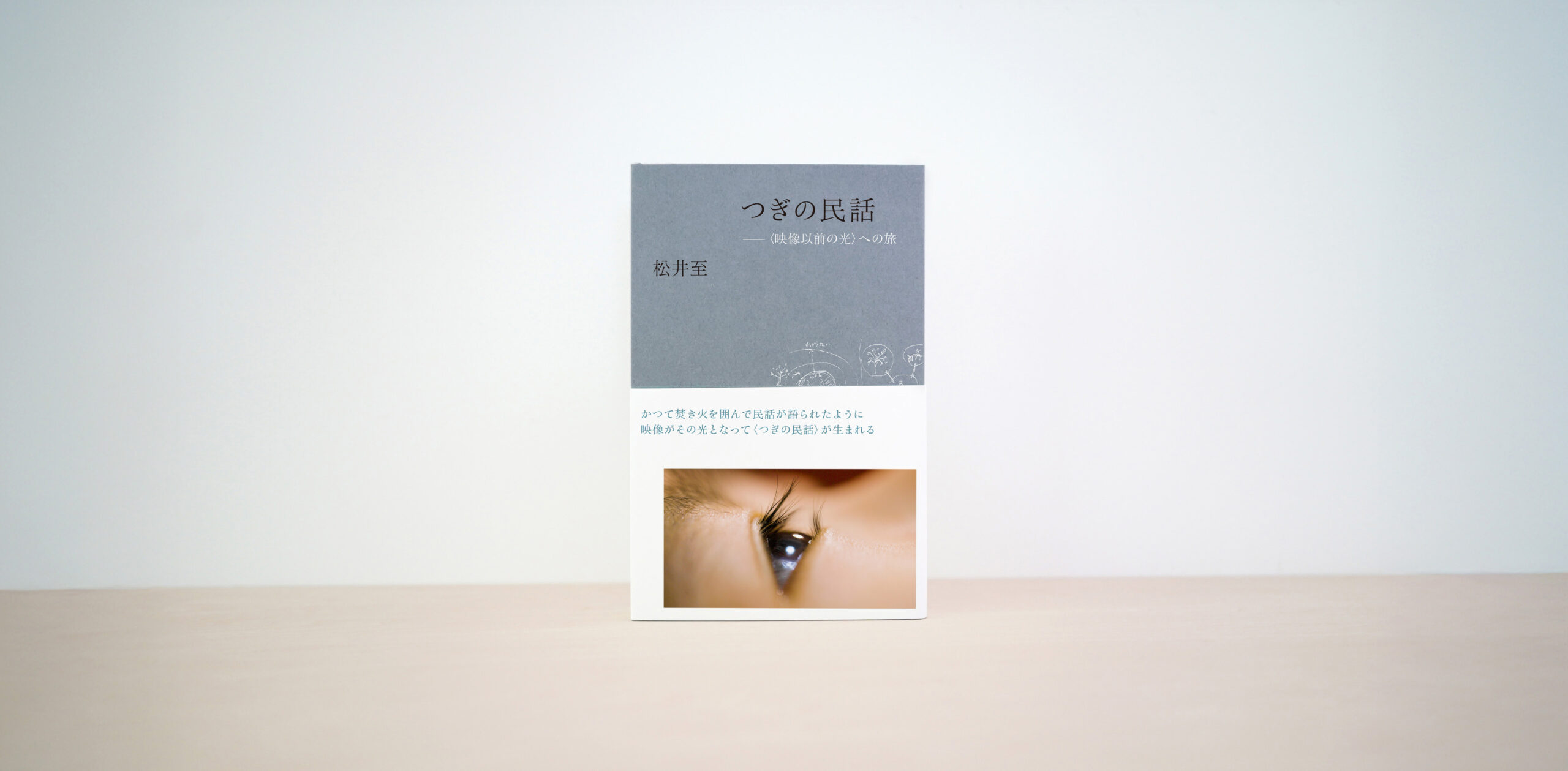
[松井至『つぎの民話』より「光を読む|映画『私だけ聴こえる』」を無料公開しています。
書籍版は【こちら】から購入いただけます]
二〇二二年春、カーテンを閉め切った暗い部屋に籠って一ヶ月ほど作業をした。長らく陽の光を浴びていない気がしていた。部屋の空調の音、台所の換気扇の音、表通りの車の音、鳥の声……そんなふうにひとつひとつ音を探し出し、ワンカットに五つも六つも重ねて、シーンに流れる空気を分厚くすることで現実に少しでも近付けようとしていた。
映像にはいつもなにか足りなかった。
ありったけの技術と思考を駆使しても、なんとはなしに過ぎていく日常の五感の機微に追いつくことができない。
映画の公開が迫っていた。
依頼していた音響効果のエンジニアに逃げられて、自分で音を探すことになった。とても間に合うとは思えない差し迫った日程だったが、撮りはじめた七年前からの映像をすべて見返して、これまでに通り過ぎて来た音の響きを聞き直す作業をはじめると、慌ただしい外界から切り離されて不思議なほど穏やかな時間に浸った。
どこに向かう予定だったのかもう忘れてしまったが、近所の公園を歩いていて、あたりが妙にまぶしくなり、なぜか「ずいぶん遠くまで来た」と感じた。足元から顔を上げると見慣れた風景ははじめて目にするように鮮明で、ありふれた事象のすべてが剝き出しのまま感覚に飛び込んできた。
ふと小道の脇から猫が歩いてきて止まり、目が合う。
一秒、二秒、三秒……猫は去る。
その軽やかな身のこなしで、見たこともない文字のような残像を残す。
猫が空気に書いた文字を目で読む。
ふとカラスの鳴き声がして上を向く。
折り重なる無数の葉が音もなく震え、その揺れ方で風の形が見える。
葉が宙に模様を描くのを目で読む。
ふと小鳥が高所から羽を丸めて落ちてくる。
地表近くではばたき、上昇する。
小鳥が空気の抵抗と戯れるのを目で読む。
なにもかもが存在するだけでしゃべっていた。
どの存在も「在る」というたったそれだけのことで命をまっとうしていた。
ぼくはこれまで猫を前にして「猫」という言葉を見ていたのだと気付いた。「カラス」という言葉を、「葉」や「空気」という言葉を見ていた。すでに世界にふくまれていて全身で関係しているというのに「世界」という言葉を見ていたのだ。いつからかはわからないがとても長い間、言語に実相を奪われていた。そして、いつも何かが足りなかった。自分をとりまく世界を名付け、分別し、対象化し、それを見ている傍観者の立場から身動きできなかった。そうやって膨大な時間を無駄にしてしまった。
目を見開くと光があり、他が見える。
たったそれだけのことのあまりにも大きな僥倖を知った。
存在は、そのまま喜びだった。
意識を覆い尽くしていた言葉の網目から一気に抜け落ちた。なんの変哲もない一日だったが、生まれてはじめて光に感謝した。それから、耳の聴こえない人たちの世界に感謝した。存在を目で読むことを教えてくれたのは彼らだったから。
映画『私だけ聴こえる』の制作が終わろうとしていた。
*
二〇一五年のある昼下がり、シャワーを浴びながら、ある詩の数行をふと思い出した。
おれは三日間音を殺してみた
おれは三日間色を剥ぎとってみた
おれは三日間形を毀してみた
『おびただしい量』岡田隆彦
詩に倣って少しの間、音を殺してみる。
商店街を走る車の音、アパートの廊下を歩く足音、体から滴り落ちる水滴の音をひとつひとつ意識から消す。
一切の音が聴こえない状態になってみる。
目を閉じると映像がやってきた。
東日本大震災直後、警報や叫び声が飛び交い、聴こえる人たちが避難して居なくなった街の一軒の家の窓から夫婦の姿が見える。倒れた家具を元の位置に戻し、停電でつかなくなったテレビを直そうとしている。ふたりには危機を告げる街の喧騒が聴こえない。何も知らず、いつもの生活に戻ろうとしている。黒い壁のような巨大な津波が、ふたりの住む住宅地の背後まで、すでに音もなく迫って来ている。
その一枚の画が脳裏に焼き付く。
風呂を出て、あの日、津波から生還したろう者のドキュメンタリーを作ろうと思った。
「どうやって津波が来ることを知ったのですか?」
宮城県の沿岸部を歩いて、ろうの方々に尋ねる。
答えの多くは、近所に住む〈耳の聴こえる子どもたち〉が駆けつけたことによって一命をとりとめた、というものだった。
その子どもたちに話を聞く。
普段から「何かあると親が困るだろうなと思って」近くに住み、震災があった時は真っ先に駆けつけたという。自分の子どもの安否を確認するよりも先に「体が勝手に動いて」実家に向かったという人もいた。
聴こえる子どもが小振りの手話のような動きで聴こえない親に話しかける。目が合うと恥ずかしそうに「手話習ったことないんで、家族にだけ通じるジェスチャーみたいなものなんです」と言う。世界でここにしかない言葉が目の前にあった。
津波で亡くなったろう者は、あの時どうしていたのか。
頭をよぎった疑問を捨て去れず、あの日亡くなったろうの夫妻の息子さんの連絡先を人づてに入手し、電話をかけた。
彼もまた〈耳の聴こえる子ども〉だった。
私は……あの日、親の近くにいませんでした。
普段、仙台に暮らしていますから。
なるべく早く実家に戻って、被災した家の階段を上ると、親は畳の上で手を繫いでふたり並んで倒れていて。死んでいました。その後、近所の人たちの話を聞くと、どうやら何度も両親を呼びに行ってくださったようです。家の目の前が小学校ですから。一緒に移動していれば助かったのに、なぜか親は行かなかったようです。手を繫いでいたので、もう生きることを諦めたのかもしれません。聴こえないので、避難生活に耐えられないと思ったのでしょうか。
……わかりません。ずっと考えてるんですけど……わかりません。
私には親のことが最後までわかりませんでした。
一定のトーンを保った礼儀正しい声に、嗚咽が混ざってきていた。自分の発した問いが、彼の心の薄い瘡蓋をめくって血が流れ出るのを見ている気がした。震災から四年が経っていたが、まだ生傷だった。
取材はここで終わった。
耳の聴こえない親と聴こえる子。
その親子は長い間ひとつの家族という親密でちいさな空間に居たはずなのに、別の惑星からやって来た異なる生きもののようにかけ離れていた。
放送後、番組のレポーターをしてもらった手話通訳士のアシュリーから「コーダ=CODA(Children Of Deaf Adults)」という言葉をはじめて聞いた。
取材でろうの人たちの子の話を聞いたでしょう?
耳の聴こえる息子や娘に出会ったでしょう?
彼らはコーダっていうの。
私もコーダです。
まだ知られていない、新しい概念なのです。
コーダについて彼女は「ろうの世界と聴者の世界、ふたつの世界のあいだで育ち、居場所を失い、ストレスに苛まれる」と説明した。子どもの頃から親の会話の通訳を強いられて、同年代の誰よりも早く大人になる。両方の言葉がわかるために心ない差別を経験することもある。聴者から「障がい者」として扱われる親を見て、まだ幼いにもかかわらず親を守ろうとする。そうして自分もまた聴者であることに気付く。こうした成長過程を経ると、成人してからも内面が不安定で、アルコールやドラッグに溺れる人が少なからずいる。コーダは世界中に点在し、自分たちが何者なのか、その定義を作っていくところだ。私たちは、ろう者でも聴者でもない。「コーダの世界がある」と言わなければならない。そうすることでコーダは、自分と同じ背景を持つ人間がいることを知り、親友を作り、恋人を作り、人生を作るのです、と。
熱を帯びてきた彼女の話を聴きながら、あるイメージに浸っていた。
がらんとした巨大なショッピングモールで、幼い自分が迷子になっている。
不安に耐え切れず大声で泣き叫んでみたものの、聴こえない親には届かない。持ちうる力を振り絞っていくら叫んでみても、親が自分の声に気付くことは絶対にない。もっとも知らせたい人に向けて、どこにいるのか、どれだけ必要としているのかを知らせることができない。永遠に見つからない迷子になって、その諦めが身体中に染み渡った後も自分だけで過ごさなくてはならないのだ。
それは恐ろしいイメージだった。
わたしの体はあなた(聴者)と同じです。
でも心の中はろう者なのです。
真っ直ぐにこちらを見ながら彼女は「コーダの映画を作ってください」と言った。
*
二〇一六年、アシュリーとアンケートを作り、SNSを通してアメリカのコーダ・コミュニティーに拡散した。回答をくれた子に連絡をとっていく。何十枚ものアンケートに目を通す。家族構成−両親がデフ(ろう者)、兄が難聴。母語は手話。年齢は十五歳。
「私はろうになりたかった」という女の子とスカイプをつないだ。
ショッピングモールで買い物を済ませて車に乗り込み、手話で父親に発進を合図し、コーダの友達とふざけあう彼女が画面に映ったとき、この人を撮りたいと思った。弾けるような声、ろうの世界で身につけた滑らかな手話、聴者の世界を観察する過敏なほど高い感受性。表情がころころ移り変わり、言語を介さなくても画面を超えて喜怒哀楽が飛び込んでくる。
名前はナイラ。十五歳の奔放さと危うさに惹かれた。
ナイラの暮らすインディアナへ、三日間の撮影に行った。
彼女からしてみれば、ぼくは遠いアジアの国から突然やってきた中年の男性ディレクターという怪しい存在だったに違いない。手話もできず、英語も片言。それでも家族で迎え入れてくれたことが不思議だった。
インタビューをはじめると、十五年間、堰き止めていた感情が溢れ出した。
子どもの頃から話すのが嫌いだった。
私はずっとデフになりたかった。
その声は、最愛の家族と一体になりたいという深い欲望と、聴者の世界に居たくないという意思で漲っていた。
手話で話すとあったかい。
目を合わせて話すし、表情を伴っているから感情が伝わってくる。
聴者の世界は目を合わさない。感情も顔に出ない。口だけ動かして話す冷たい世界。
相手の表情を読み、互いのまなざしを受け入れ、注ぎ、顔も体も〈言葉〉にして話すこと……ろう文化にあたりまえにある親密さ……それが聴者の世界では失われてしまう。だから家族やろうのコミュニティーにいると、なぜ「私だけ聴こえる」のだろうと不可解に思う。
「ろうになりたかった」のに、と。社会からは聴者として扱われ、心の中ではろうの世界への帰属欲求が強まっていく。どこまでいっても一体になれない。「聴こえる」という確かな感覚を消し去ることができない。
ろうの世界と聴者の世界のはざまを行き来するナイラに「ろうになりたかった」と言わせたのは誰か。社会の定義した障害と健常という分別が、差別や断絶もふくめて親子間に固着し、コーダはそれを選択の余地なく内在化したのではないか。
同情しないで。
私がどれだけ幸せか知らないくせに。
あの時、ぼくを射抜き、ぼくの背後の無数の聴者を射抜き、聴者中心の社会をも射抜いて彼女は泣いた。それを聞いてしまったからには、できる限りを尽くして人々の善良さの元へと運ばなければならなかった。
東京に戻り、ドキュメンタリーの国際企画会議の準備をはじめた。世界の制作者たちにコーダの存在を伝えようと三分の映像を作った。その知られざる物語は、驚きと共に迎えられ、インドやカナダの映画祭に招待された。映像を観たナイラから、返信がきた。
かわいそうな人だと思われたくない。
そこにはナイラの葛藤を表す涙や、悲劇的な音楽がふくまれていた。
「コーダのことを聴者に伝えるには、わかりやすい演出で物語を作る必要があるんだ」と言い訳めいた説明をすると、彼女からこう返信があった。
私の物語は私のもの。
コーダにしかわからない。
あなたはコーダではないのだから、理解できると思わないでほしい。
何度もナイラの言葉を反芻した。
私の物語は私のもの
私の物語は私のもの
私の物語は私のもの
強く、正しく、何も付け足すものがなく、その言葉に反射した自分の姿は醜かった。相手をわかろうとする過程で、当事者の心を遮って代弁しようとしていた。しかもそれを「職能だ」と開き直っていた。映像は他者の人生を強引に一般化する暴力性を常に持つ、という単純な事実を受け入れることができなかった。コーダという小さくて繊細なコミュニティーに、一時入ることを許されただけの聴者が、〈コーダとは何か〉を定義してしまいかねない映像を作り、その負荷をナイラひとりに負わせてしまっていた。
映像を見ると吐き気をもよおすようになった。
それから一年ほど連絡は途絶え、制作に向き合うことができなかった。
二〇一七年、ナイラの母からのメッセージでプロジェクトは再開した。
「娘は『これまで撮った映像をなかったことにしてしまうのは違う』と感じていて、『撮影を続けたい』と言っています」
空港からタクシーで郊外にある彼女の家に向かう時、自分には何も方法がないと思ったことを覚えている。ああしようこうしようと構想を練ること自体が傲慢で、いかにも撮る側がエゴイスティックに制作を進めようとしている証拠のような気がして、彼女の家に着く頃にはすべての計画を手放していた。コーダを撮ることができないという実感だけがまっとうに思えた。
彼女に会って、言えたのは一言だった。
ぼくにはコーダのことはわかりませんでした。
あなたがディレクターになってください。
そう伝えると、ナイラは満面の笑みを浮かべた。
自分の人生を他人に代弁されたくはないけれど、表現はしたい。
自分だってそうだ。誰だってそうだと思う。
それを機に彼女の口から聴者、コーダ、デフの友人とのやりとりや、近々の予定がどんどん出てきた。それに対して「こんなシーンができるよ」と即興的にイメージを伝え、共にシーンを妄想しながら、ロケを組み立てていった。撮影の前日、決まって四、五時間話しこむようになり、「わたし(撮影者)があなた(被写体)を通してコーダを描く」のではなく、「あなたとわたしとでコーダとは何かを探索する」ことに制作の重心が移っていった。
〈撮影者〉と〈被写体〉という構図を忘れて、構成もなく、待ち合わせの場所だけ決めて、あとは直観的に撮るやり方に慣れていくと、ふと映像で彼女の日記を書いているような感覚になった。ナイラと話しながら横を歩き、いつのまにかナイラが自らの物語を全身で綴りだす頃には、ぼくの存在は消えているべきだった。そうすることで彼女自身がこの映画を動かしているという主体性が立ち上がり、映像に現れることを願った。他の三人の主人公たちとも同じように話しこみ、探索した。何を作っているのかも実のところよくわからなかったが、コーダたちが自分の苦労を誰にも奪われずに人生を紡ぐ姿は美しかった。
あのときぼくにできたのはコーダのまわりに居ることだけだった。
交わされる言葉の意味はわからないまま、ただ見ることを許された。
レンズを通して手話の世界に触れた。
聴者が口語に抑揚をつけて意味合いを調整するように、ろう者やコーダは顔の表情やジェスチャーで意味合いを調整する。そうやって相手を読むことで鍛えられた彼らの目の能力にたびたび驚愕した。ほんの少しの時間を共にしただけなのに「あの人は自分の言いたいことを言っていない」と見抜いたり、視界に入っていないはずなのに誰がどう動いているのか把握している。凡庸な五感しか持ちあわせていない自分には、特殊能力としか思えなかった。
彼らの目にこそ本来の野生があり、五体満足なはずの聴者の目はその能力を十分に使い切れずにむしろ社会的に抑圧されているのではないか。
〈障害〉という概念が覆った。
聴こえないことによって、脳の視覚野の領域が拡張することで、目から兆しを読み、他者の心を読み、事象の響きを読むことが可能になるとしたら、それはもう障害ではない別のなにかだ。
ろう者やコーダは〈見る〉という行為そのものの自由をも拡張しているようだった。
その目で世界を見てみたかった。
その目なら存在がなにをしゃべっているかわかるかもしれない。
*
あなたはコーダのことをまったくわかっていない
モスクワで行われたろうの国際映画祭で、観客のひとりからこう言われた。『私だけ聴こえる』を上映した直後、五十代後半くらいの男性が強張った顔でぼくを睨む。
私は私の人生でたまたま出会った人たちと縁あって映画を作りましたから、あなたの考えるコーダではないかと思います。
そう答えて去った。
夜の道を歩きながら、おそらく彼はコーダだろうと思った。
そして、おそらく彼は映画ではなく、自分の人生を見たのだ。
わたしもコーダです
二〇二二年、『私だけ聴こえる』は全国で劇場公開された。各地の映画館に挨拶に行くたびに会場でこんなふうに声をかけてくれる人がいた。制作の七年間、まだ見ぬコーダに手紙を書くように作った。やっとその返信が来たような気がして、決まって小さく控え目なコーダたちの声を聞くのが嬉しかった。
ある若いコーダは映画が始まってから終わるまでの七十六分間、ずっと静かに泣き続けていた。その小刻みに震える肩でわかった。上映が終わると「松井さんはコーダなのですか?」と聞かれた。「いいえ、聴者です」と答えると満足そうに帰っていった。
ある女性は「アシュリーが妊娠した時に『自分の子どもはろう者かもしれない』と戸惑う気持ちは私にしかわからない」と言って大粒の涙を流した。
ある年配のコーダはSNSを通してぼくにたくさんの質問を投げかけたが、劇場には来なかった。「映画を観ると、自分の子どもの頃を思い出して、半月は何も手につかなくなるから」と言った。
サインをしている時に「映画に出ていたコーダみたいに、みんなが手話をできるわけではありません!」と強く言われたこともあった。
あるコーダは「自分がコーダであることを誰にも伝えたことはないし、同じコーダの集まるコミュニティーにも行く気はない。傷の舐め合いはしたくない」と言うのだった。
何も知らずにふと映画館に入ったけれど「全部自分のことだった」と言う人もいた。
モスクワで睨みつけてきた男性は、ぼくに伝えたかったのかもしれない。
俺はもっと苦しかった
俺はもっと苦しかった
俺はもっと苦しかった
映画の光に向かって自分の苦しみを確かめ、ぼくをわずかでも不快にさせることで自分の人生に無理矢理にでも形を与えたい衝動に駆られたのか。光は忘れ去りたい記憶までをも照らし出すものだ。
だとしたら、明るみに出たその記憶は、その瞬間から彼の物語になったのだ。
「私の物語は私のもの」。
映画の向こう側にはいつもただ異なる生があるだけだ。
コーダはろう者と聴者の間で通訳者になる。
ぼくはそのコーダという存在の通訳を試みた。
コーダはいくつかの真実を残していった。
人はそれぞれ自分にしかわからない苦しみを生きること。
その苦しみには本来的に名前がないこと。
異なる世界を行き来して他者を読み取ろうとする者は、おのずと通訳者になること。
そして目は光に許されてあらゆる存在を読むということ。
〈光を読む|映画『私だけ聴こえる』〉了
松井至[まついいたる]
1984年生まれ。人と世界と映像の関係を模索している。
耳の聴こえない親を持つ、聴こえる子どもたちが音のない世界と聴こえる世界のあいだで居場所を探す映画『私だけ聴こえる』が公開され、海外の映画祭や全国40館のミニシアターで上映され反響を呼んだ。令和4年度文化庁映画賞文化記録映画大賞受賞。
誰からでも依頼を受けるドキュメンタリーの個人商店〈いまを覚える〉を開店。
日本各地の職人と自然との交わりをアニミズム的に描いた〈職人シリーズ〉を展開。
コロナ禍をきっかけに、行動を促すメディア〈ドキュミーム〉を立ち上げる。
無名の人たちが知られざる物語を語る映像祭〈ドキュメメント〉を主催。
仕事の依頼などは 【こちら】まで。
最新記事
- ソラノマド|高山なおみ
雪の日2026年02月18日 - 柳亭市若さん
如月の落語会
「看板のピン」2026年02月07日 - 松井至『つぎの民話』
刊行記念 上映+トーク
〈名前のないものを共に見る〉
@ Readin’ Writin’ BOOK STORE2026年01月28日 - ソラノマド|高山なおみ
ラジオの声2026年01月27日 - 映画とごはんの会〈アンコール〉#01
『武州藍』2026年01月22日
アーカイブ
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年4月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年6月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年2月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2015年9月
- 2015年4月
- 2015年2月
- 2014年11月
- 2014年9月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2013年8月
- 2013年6月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月