2012年11月14日
「たべる」ことと
「たべられること」について
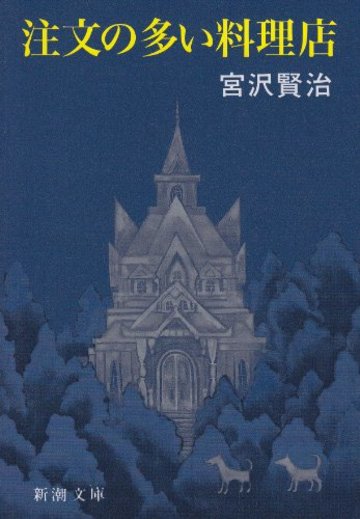
以下に掲載するのは、ちょうど一年前に、祥見知生さんの企画された展覧会「TABERU」のために書いた文章です。
はじめて宮沢賢治に触れた原体験のこと。
書いたことすらすっかり忘れていましたので、新鮮な気持ちで「そうそう」とうなずきながら読みました。自分にとって賢治の存在はかなり大きいのだなあ、と、この歳になって改めて思います。
書く機会をくださった祥見さん、ありがとうございました。
/
「たべる」ことと「たべられること」について
——『注文の多い料理店』の記憶
宮沢賢治は怖い。怖いけれど、どうしても惹かれてしまう。作品の向こうには濡れたおしめの中のようにじっとりと生暖かい、不思議に心地好い世界が広がっているようで、はじめて出会った時から好きと嫌いを超えたところにいる特別な作家になりました。幼い頃、寝物語に父が童話を読んでくれました。その定番が「注文の多い料理店」であり「どんぐりと山猫」であり「なめとこ山の熊」であり「セロ弾きのゴーシュ」であり「風の又三郎」でした。煙草の匂いのする父が、賢治独特の言い回しを節をつけて読むのが面白く、まぶたの中に広がる湿り気のある東北の冬の風景に震えながら、動物たちと話し、最後はなかば夢の中で例の濡れたおしめのような何とも言えない安心と不安のない交ぜになった気持ちのまま眠りに入りました。
「注文の多い料理店」では、自分はいつしかふたりの紳士を食べてやろうと思っている「きょろきょろ二つの青い眼玉」の持ち主になって、クリームを塗りたくった紳士の生白いからだを「美味しそう」と思っていました。がらがらと崩れ落ちるようなクライマックスを経て紳士たちは助かる訳ですが、ぼくはいつも「ああ、もう少しで食べられたのに」と悔しい思いを噛みしめました。と同時に、自分がむしゃむしゃと食べられる瞬間も想像していました。ばりばりと骨が砕け、肉が引き裂かれて、さぞや痛いに違いない。こころのどこかで、何かの食べものになることに、どこか甘美なよろこびを感じていたようです。それが先に書いた「濡れたおしめの中」のような感覚につながっていたように思います。
少し脱線をお許しください。そんな風に賢治を読んでいた自分は、次第に人間以外の生きものや風や川や林といった自然ともきっと話が出来るはずだと確信するようになります。幼い自分のまわりに起こる小さな不思議(例えばいつも小さな竜巻が枯れ葉を舞い上げている細道とか、風もないのに動いている木の葉とか、誰もいないのに時おり聞こえる笑い声とか)を、そう思うことで受け入れようとしていたのでしょう。そして、いつか気がつきます。「怖い話」「怪談」などと呼ばれるものは、人間以外の存在と対話を果たした人の記録に違いない。いまの文化には「怖い」「怪しい」という価値観しかないけれど、その先にはもしかすると賢治が描いたような動物たちと世界の成り立ちについて話し合い、いのちのやり取りをするような世界があるのではないか、と。
20代後半から30代半ばにかけて、編集者としてのかなりの時間を「怪談」の蒐集に費やしました。体験者に直接会って話を聞き、記録する。1冊に100話を収録した本を、10冊作りました。合計1000話。収録できなかった話も当然たくさんありますから、取材した体験の数は優に5000を超えるでしょう。そんな気の遠くなるような作業を裏打ちしてくれたのは、怪談という薄暗い入り口ではあるけれど、その道を歩き続ければいつか思いがけず陽の光に満ちた場所に出て、わたしたち人間は種を超えて、時空を超えて語り合い、励まし合い、いのちを交換し合う場所に出られるのではないか、という祈りのような思いでした。
アノニマ・スタジオを立ち上げたとき、出版のテーマを「ごはんとくらし」に限定しようと決めました。編集者としての色気はほかのジャンルにもありましたが、自分がすべきはこのジャンルだと思いました。怪談の世界のキャリアを知っている人たちはその世界から逃げたと思ったようです。しかし自分の意識は違っていました。ごはんの世界こそが、いのちの交換の現場に違いない。毎日のことだから、ごはんは人が人らしくあるための基本だと思ったのです。人のからだは、口から入った食べものと飲みもの「でしか」作られない。としたら、食事のことを充実させることは、そのまま人の存在を充実させることに違いない。
ここでくるっとひとまわり。
宮沢賢治が教えてくれているのは、(少なくとも自分にとっては)いのちはまわっているということです。宮沢賢治の作品が怖いのは、そのことがあまりに自然に示されるからだと思います。そのまわっているいのちの輪の中で、じぶんはどんな存在だろう。そう考えるとき、人は底の見えない深い井戸を覗きこむことになります。いのちを奪ってしか生きられない存在に、救いなんてあるのだろうか。
人は誰かほかのものの餌になることだってある。そのくらいにこの世界は平等です。餌になるときに、少しでも消化しやすい、相手の負担にならない、できれば美味しいと思ってもらえるからだでいることは、生きものとしての最低の節度なのかも知れない、などと考えています。
最新記事
- 丙午 2026年
今年もよろしくお願いいたします。2026年01月01日 - ソラノマド|高山なおみ
踊り場の小窓にて2025年12月25日 - 柳亭市若さん
師走の落語会
「掛け取り〜2025有馬記念〜」2025年12月08日 - 第34回 映画とごはんの会
伊藤碩男翁追悼
『山に生きるまつり』2025年11月20日 - ソラノマド|高山なおみ
ぼくらは森へかえることにした2025年11月14日
アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年4月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年6月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年2月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2015年9月
- 2015年4月
- 2015年2月
- 2014年11月
- 2014年9月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2013年8月
- 2013年6月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月


