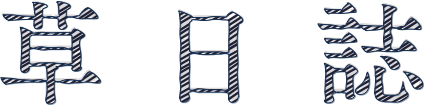2024年7月5日
人に潜る 第7話
「いのちの被膜」をめぐる対話
〈後編〉

2023年夏、京都の誉田屋源兵衛にて。
短編ドキュメンタリー『いのちの被膜』は山口源兵衛さんからの依頼を受けて松井至が制作した作品である。そこで語られた衣をめぐる思考を深めるため、思想家の清水高志さんをお招きして上映と対話が行われた、その記録の〈後編〉。
六、凧の裏の世界

松井__せっかくなので子ども服を見せていただきますか。用意してもらっています。
源兵衛__これが背守り。
清水__あっこれがそうなんですか。これですか?

源兵衛__背守りいうのは「こういうものや」というのは無いんです。ただ、一説には子どもの身幅やから背中を縫うてないんですね。大人の着物は全部背中に縫い目が入ります。子どものは無いでしょう。せやから余計に悪魔が、悪鬼悪霊が入りやすいと。なんかけったいな話やなと思ったんやけれど、この「縫う」という行為の中にそういう封じ込める力があるっていうね。せやからそれが無いから、子ども服に背守りをつけたという説もあるんや。それは一概に否定はできないんですけど。
清水__やっぱり糸が裏と表を行き来するという行為だから……。
源兵衛__せやからもう糸があるということも縫うことも贅沢な話やから。何にもない人は松葉を刺したんです。絶対に背守りはなかったら子どもは悪鬼悪霊に襲われる。背中から忍び寄ってくるというのを、みんな信じてた。
清水__魔よけなどで目の模様をつけるとかいうのは東南アジアでもありますね。
源兵衛__背守りいうのは決まりはないから、もうそれぞれ自由につけている。
清水__こんなものを作ってもらったりするのも結構恵まれたおぼっちゃんなのに、儚くすぐ死んでしまったりするんですね。
松井__これは足袋ですね。

清水__わぁ、小さいですね。
何かこういうのを見て、だんだんしばらく経ってくると何か自分がこれ(足袋)を履いていたような気持ちになってくる。幼年時代、自分もこんなものを履いていたという錯覚すら生まれてきますね。
源兵衛__まあ裸足で走り回ってたやろうな。普通、大人も。
清水__怪我したりしないのかな。
源兵衛__せえへんし。痛いとも言わへんし。
松井__むしろ衣服があまり無かったころのほうが体は強かったのかもしれないですね。
源兵衛__それはそうやろね。もう江戸でも真冬で裸のやつがいっぱいおったんやから。
清水__うちもね、弟が小さいうちに母が編んだセーターとか、ずっと残っていますね。
何か青いセーターにこういう絵を描いてくれとか言って、その当時おふくろは下絵のまま作って、タイガーマスクの顔なんか作って、ほんとうにタイガーマスクになっているんですけど。そういうのはいつまでも物置に残っているんですよね。
源兵衛__そらね、子どもはこれでうろうろしよんやから。せやけどまあ裸足でうろうろしてるやつがいっぱいおったんやからね。こんなん履かしてもらえるいうのは、ありがたいわな。
松井__それだけ薄着だったんでしょうね。
清水さんに映像をはじめて観ていただいた時、魂はどこにあるかというと人をくるむもの、被るもの、包むものの方が生命なんだ、ということをおっしゃっていたと思うんですけど、そうした考えはどこからきたのでしょうか。
清水__『ソウル・ハンターズ』という面白い本があって。さきほど狩猟の話をちょっとしたけれど、ロシアのシベリアの北の方にユカギール人というモンゴル系の少数民族がいて、その猟について書かれているんだよね。
シベリアの森には巨大なエルクっていう鹿がいるんだけど、それを狩るのにサウナで自分たちの体臭を消して、鹿の皮のついたスキーを履いて、角までつけて待ち伏せるというんだよ。するとエルクが、まるで自分の理想像が現れたかのように喜んで出てくる。エルクにしても、自分がどういう姿なのかよく分かっていないので、惹かれるらしいんです。狩人も一対一になったらエルクに魅入られてしまう危険がある。自分たちにはたくさんの魂があって、そういう逃げ場があるからなんとか狩ることができるんだというのが、彼らの主張らしいんです。着脱自在みたいな感じで、外側に現れているガワがその人の真実である、というきわどい局面をこの狩猟の話は逆に物語っていると思う。
世界がいろんな風に見えていて、みんなが同じ世界を見ているわけではないというのは、狩猟民にとっては当たり前の感覚のようだね。
松井__それはエルクの側から見た世界は、人とはまた別という。
清水__それぞれのパースペクティブは別で、魅入られるというのは、エルクの世界に引き込まれてしまうというわけ。
松井__人の側もふと獣の世界に引っ張り込まれちゃうんですね。
清水__狩猟のときに弾を外すと、シカが馬鹿にした顔でこっちを見てくるとか、そういう奇妙な感覚はアニミズム的な狩人には親しいものらしい。シカの娘たちの世界に狩人が導かれて、雌と子供は撃たないでくれと言い含められて帰ってくるとか、そういう物語があるけど、それは違うパースペクティブのなかに引き込まれるという話なんだろうね。
洞窟のなかに戻るとクマもズボッと毛皮を脱いで人間になっているとか、わけが分からない(笑)。そういえばOSO18と名付けられた熊がいて、六十頭あまりも牛を襲ったのが、毛が擦り切れるくらい隠れて隠れて隠れまくっていたんだけど、この前あんまり暑いから麓に降りてきて撃たれちゃったらしい。なにかその話を聞いて横井正一さんみたいな生活をしてたんじゃないかと思った。(笑)
松井__森の中で潜伏を続けていた熊。
清水__暑すぎて恥ずかしながら降りてきて撃たれてしまって。でも、実際すごく人間ぽいみたいですね。熊も。毛皮を剥ぐと、本当に人間みたいな形になるらしいです。
松井__ああ、なりますね。皮をとると人型にかなり近い。羅臼で熊を撮影したことがあるんですが、遠くで這っている姿は人型に見えましたね。
清水__動物は相当人間くさいですもん。猫も目が合ったりすると相当意思が通じますよね。
源兵衛__通じる。犬でも通じる。
清水__通じますよね。あれ不思議だな。このあいだ麻薬捜査犬がテレビに出てきたんですけど、麻薬捜査犬って匂いでわかるらしいんですね。麻薬を見つけると尻尾を振るんですよ。褒めてもらえると思って。うれしそうな顔をして麻薬を見つけていて。なかなかいいもんだなと思いました。世界中のあらゆる地域で、さまざまな動物を使ったりしているんですよね、人類は。それが種としての人類の定義にすらなっている。
最近ミシェル・セールが書いていることで面白かったのが、道具というのは、人間の手一本の延長とかそういうものではなくて、一番基本的な道具というのは人間が人間を使うことだって言うんだよ。人間の集団がやることを機械に置き換えたのが道具だと語っていて、これはなるほどなと思った。何かと何かが結びつくということだって、人間と人間が肩を組んだりくっついたり離れたりすることを、紐というものでやってみようとか、それで石と棒をくっつけてみようとかいう風に工夫するわけじゃないですか。やっぱり集合的なんだよ。道具って。継ぎ足して延長していくことじゃなくて、人間と人間、人間と動物のうごめく相互関係が道具性のもとになっている。
松井__ミシェル・セールは、最初の道具は紐であるという話が印象的でした。
清水__紐だと言ってるし、そのさらにもとは集団の相互関係だと言うんだよ。よく主客二元論的に、メディア論でも道具というのは、たとえばバナナを取るのに手が届かないから棒を使うといった、延長だという風に説明するけれども、実はそんな意図を超えたものとして道具というものはある。
インターネットを通じて受け取られるものも、もはや誰の意図をも超えているし、何かの延長などというものじゃない。そう考えると最初から社会的なものとして道具があったというのはすごく鋭い指摘だなと思う。
松井__なにか人間の関係自体が見えない紐のようなもので。結びつけられたり、解かれたりする。そういうイメージですよね。
清水__がっちり腕を組むとか、くっついて何かするとか、網をみんなであげるとかいうのもそうだし、道具はその媒介としてあるということを考えてるんだろうね。道具というものの、用途も不確定なポテンシャルは、もともと集団性に根ざしていたし今後ますますそうなっていくと。
昔は主客二元論で、世界には多様な要素、データがあって、それを整理・統合してコントロールするのが人間であると考えられていた。こういう図式は21世紀になって幾分変わってきていて、さまざまなコンテンツや情報も今はネット配信されるけど、それらは結節点的な対象で、無数の人たちがいろいろアプローチをして、予期不能な集団球技のような状況があちこちで発生している。道具やものはそれを可視化する媒体になっているよね。
松井__僕はドキュメンタリーを作る時に主客二元論の限界を感じていて、カメラを持っている人が一方的に相手を撮る、被写体が撮られるという構図だと思われがちなのですが、それは実際に現場で起きていることではないと考えています。それだとshooting(銃を撃つ)になってしまったり、take(盗むの意味で使われる場合)のイメージがある。昔から「写真に撮られると魂を盗まれる」みたいな怖いイメージがあったし、いまだに撮影者が暴力的にふるまう構図が通念として自分の中にもあると思っていて。
「そうじゃないんだ」と気付かされたのが今回の子ども服の話でした。
というのは「見る」ことが人を育ててきた光のように思えたんですよね。母親が子どもを見る。よくよく観察して、この布でこの大きさにしようとか、足が痛むから足袋はこういうふうにしようとか。目に入れても痛くないという言葉があるけど、包み込むような「見る」がそこにはある。衣が出来上がる以前に、つぶさに見ている目がある。
まなざしというものが相手と対立するものでなく、あなたとわたしを分けるものでもなくて、相互に浸透する。同化のためのまなざしだったり、そこで自他が育つためのまなざしというものがあるんだということを衣から教わる感じがするんです。親が「見る」ことの中で子どもは育つじゃないですか。
清水__フランス語でComprendreという言葉があるんだけど、これは「分かる、理解する」という意味であるとともに「包む」ことをも表わすんです。そういうふうに分かるということが、やっぱりあると思う。こういう衣が包み込むような感じで分かるということが。そういう触感のような分かり方が大事だし、かつての民藝運動のようなものが、理論としてもアップデートされてゆく必要がある。
柳宗悦を今読むと、案外仏教の理解に時代的な制約があるなとも思う。トルストイ的な民衆礼賛で、易行道の仏教の要素しか汲めていない。明治以降の知識人は空海や密教にほとんど手を付けられていない。その辺もちゃんと筋を通して日本文化を全部、触感でわかるようにしないといけないと思う。
松井__感覚を自由にする、皮膚を自由にするということが普段案外できてないのかなと感じていて、物を見ることから撮影を通して模索していくと、見ることの内に触れることも含まれてくるし、その領域には死者も存在する。映像は見えない紐になって、死者を感じさせることができると思います。源兵衛さんの後ろでカメラを持っていると、実にさまざまな風景がフィードバックされてくる。衣から来るわけです。皮膚が、五感が開かれていく。
清水さんが先ほどおっしゃってたみたいにプラトンを読み込むと時空を超えてプラトンと話してる感じになったりするんじゃないですか。
清水__それがね、するんですよ。プラトンの時代の人は文字に依存する後の時代と比べて記憶力がものすごく良くて、聴いたままを後でかなり再現できるし、どこかで見てきた情景を語ったりしても非常に生き生きしているんだよね。おそらく録音したようにそのまま覚えているんです。対話そのもののうちにも応答やリアクションがあるし、入り込んでいくとただ受け身で読んでいるだけじゃない、臨場感があるんだよ。
実験で聴覚や視覚、体勢感覚など複数の情報を使って外的世界とのインタラクションを作ると、例えば視覚はカメラに映った画像を電気信号にして刺激として送ったとしても、盲目の人でも見えるような感じを持つという、それに似たものがありますね。ソクラテスはこの角度から見るとこんな風に喋っているはずだとか、そんな風にリアルに感じられてくる。
もともと複雑に言語を発達させてきた人類は、何より聴覚優位だったはずだし、それによって情報や経験を共有してきた。人間の脳で視覚を司っているのは後頭葉なんだけど、これも一時間くらい目隠しをしているだけで、徐々に他の感覚に対応するように置き換わってくるらしいね。だから眠っているときに夢を見るのは、後頭葉を視覚的に興奮させ続けないといけないからだという説がある。
実際、空海が若いころ洞窟で虚空蔵求聞持法の修行をして、ひたすら真言を唱え続けたというのも、そういうことをやったらあっという間に後頭葉は視覚ベースじゃなくなってくると思うんだよね……。この修行をすると記憶力が非常によくなると言うんだけど、いわれがないことではないんじゃないか。よく密教では月輪観とか、日輪観という修行をするけれども、あれも結局月を観相して新月になるまでを瞑想するとか、太陽を観相して日没に至るまで瞑想するとか、視覚の要素を減らしてゆくというものなんじゃないか。
真言や念仏をずっと唱えるとか、そんなことをするのも、もともと人間が持っていたポテンシャルを引き出すためにそんなことをするものなのかなとも思うね。
松井__ああ、ポテンシャル。源兵衛さんはよく直観だっておっしゃっるじゃないですか。文献ではなくて、情景を思い浮かべたり、物語を感じるために衣に自分を合わせていくわけですよね。源兵衛さんが見ている原始布のある風景は残念ながらいまはもう残っていないし、旅の頃が最後だったかもしれないけれども、物への感じ方の更新や読み取り方の自由はまだまだできる気がするんですよね。
撮影の時にすごく本質的だったなと思うのは、源兵衛さんが珍しく体調を悪くして撮影のあとにすぐにお帰りになったんです。子ども服を感じるためのある弱さというか、揺れている状態にあって、衣から物語を読み取るために少し体調を弱らせて向こう側が主体になるような心身の調整をしていたんじゃないのかなという。
源兵衛__そんなことないけどな(笑)
松井__そんな気がしたんですよね。
源兵衛__たまたまやな。
松井__いい状態で撮影できたと思いました。
清水__岩田慶治さんが、よくフィジオノミー(Physiognomy、観相学)ということを言うじゃないですか。手相を見るように、大地の相を読まないといけないんだと。ここの土地にはあり得べきこういう経路からこういうものが運ばれて、このように人々が賑わってということを読み取る力が、アニミズムを理解するのには必要だと言うんですね。
松井__瞬間に感じとる世界ですよね。
清水__源兵衛さんがこういうものを見て感じているのも、それこそ手相を読むようなフィジオノミー(観相学)の感覚だと思うんですよ。岩田慶治さんがすごいなと思うのは、京都の疏水のわきにバスプールがあって、彼はいつもそこを通っているんだけど、ある朝突然、観光客の老夫婦に「これは何のための空間なんでしょう?」と訊ねられたと言うんだよね。当然バスプールだと思って、自分はそんなことを考えたことはなかったと。そしてそこから、ここは「いずれものの充ち満ちた空間になる」、それは「仏陀に満ちた場所だろうか」と岩田さんは自問しているんですね。これはある本の冒頭の短い挿話なんだけど、彼がフィジオノミー(観相学)と呼んでいるのはこういう発想なのかと、僕はピンと来た。今空っぽなところに、ものや人の往来を幻視する……。そこには何かが生き生きとあったし、またあるようになるんだということを感じる力。
松岡正剛さんの好きな蕪村の句に、「凧きのふの空のありどころ」というのがありますね。凧が空と一体になってはためいていて、しかしその裏に隠れている空というのは、昨日の「空」であるかも知れないし時を超えている。どんな結節点になるかもしれないものが、ニュートラルな感じでそこに潜んでいる。
枠の中にガラスが張ってあって、それで海中を覗く《タコ眼鏡》っていうものがあるでしょう? 覗くと魚がいるかもしれないし、珊瑚があるかもしれない。フィジオノミーというのはそういうものの観かただし、源兵衛さんが衣を見てわーっと感じてくるのもそういうものなんじゃないか。

松井__すごくビジュアルだなと思って。源兵衛さんはふとこう中空を見ながら話すんですよね。衣を前にしていても。その姿を見ていると、なにか源兵衛さんがその《タコ眼鏡》を通して、その先で情景が今動いているんだなという感じがして。なので、その先にある情景を僕も共に見たい。共視して、映像化してみたいと。それではじめての試みですがフィクションのパートも入れて短編を作ってみたということだったんです。
清水__そこで見えてくるのが、現在ではない何かですね。
松井__そうなんですよね。いわゆる再現シーンとも違う不思議な時間の感触がありました。子ども服をお借りして、それを自分の子に着せて撮影したというのもあるのですが、衣を繕った母のまなざしとカメラとが重なっていくような感覚でした。
清水__凧の裏の世界。
源兵衛__絶えず思うんやけど、なんか空けてないとだめやなというね。
こう……詰まってたらだめやなと。絶えずそこは空いてるみたいな、そういうものがないともう無理です。
清水__ギッチギチになっていたらだめで。
源兵衛__もう絶対無理やねん。何か空けている。
清水__違った回線が入ってくるという感じ?
源兵衛__そうそう。それは空けとかんと。
せやからこう、町とかも空き地があったらみんな何かで埋めてしまう。その何か空けているということがないと。僕らがものづくりとか、いろいろなことをやっていく時には空いてないとそら無理やわね。
清水__どこかに虚ろさというか、そうしたものがないといけないんですね。
源兵衛__ないと無理やね。
清水__プラトンの時代でも、さっき経糸と緯糸のすべてが編み込まれ、ぎちぎちに構成されて最後に魂が成立するわけじゃなくて、そのまえに魂(もの)がある、と言ってたのもそこだと思うんですよね。もっと隙があるところに、何か振動するみたいにシンクロしてくるものがあるというのが本当なんだと。

七、いのちの被膜
源兵衛__せやけど、どんどんどんどん人間は堕落しとるんやね。
それはものすごい……言うたらね、昔いくほど地獄やからね。その時に高まんやね。ルネッサンスもそうやもんね。地獄の時代。
松井__撮影の時も「昔は死が近かったから命が濃かった」というお話をされていましたね。
源兵衛__時間が濃い。本当にこう空気も濃いしね。もうそういう中というのは、命が短いということも、もちろん大事やけど、すごいこう充満しているよね。
松井__映像の最後のセリフにもなったんですけど、胞衣についてお聞きしたくて。
撮影時に僕が質問をしたのは、「子ども服ひとつひとつに母親がどうにかしてこの生命を包まなきゃいけない、生まれてきたものをもう一回包もうとする本能のようなものが働いているんじゃないか」というものでした。
それは母親が自分の胎内で、既に胎児を胞衣で包んでいた。それが出産で出てきた。もう何にも包まれていないその子の体をもう一回何かで包む。もともと内臓としてあった胎盤の延長に衣を見ているのではないかと思ったんです。
それに気づかれたのは子ども服を集めた経験からだったんですか?
源兵衛__いや、それはね。胞衣に対する意識がずっとあるんです。
繭もそうやけど、あれだけの虫の一番危険な状態を繭でこう守るやん。胞衣もそうやろね。それが出てきて。3歳ぐらいまでは胞衣の延長みたいなものを作りたいな、という。僕は作らんでも、誰かが作ってくれたらええんやけど。3歳ぐらいまではまだ胞衣の延長が必要というかそうあるべきやというのはある。まあ3歳越えたらもうしゃあないなと思うけど。3歳までやね、なんとなく。5歳というのはちょっと。
そういうものでくるむべきやね。
清水__ミシェル・セールが言うには魂というのは皮膚にあるんだと。
皮膚には自分自身で触れられるし、そのときにはその一点で主客が交わっていて、内と外が入れ替わる境界でもある、そこが魂なんだという言い方をしていて、それはやっぱり衣にも言えることなんじゃないか。
源兵衛__せやから脳やとか言うてるけど、こう身体全体っていう感じがするよね、子どもというのは。それをこうやっぱり3歳まではくるむべきだという。まあそういうもんが作れなあかんなというのはある。
松井__僕が驚いたのは「衣やなくて被膜なんや」とおっしゃっていて。
源兵衛__せやからそれを言いたかった。
松井__僕らは衣服を着ていて、あまりに日常的にこれがあるから最初からあるような気がしているけれど、衣がどこから来たのか、衣が何を外在化したものなのか、おおもとは何か。皮膚の上にもう一枚皮膚を着るみたいな、そういうイメージですか。
源兵衛__そういうイメージやね。被膜や。衣までいくのはもうちょっと先で、被膜を着るべきやと。3歳までは。
松井__被膜の「被」の漢字が僕は皮膚の「皮」がいいのかなと思ったんですよ。それで最初それでテロップを入れてお見せした時に、「皮」じゃなくて、被る方の「被」がいいとおっしゃったじゃないですか。あれはどうしてですか。
源兵衛__あれはやっぱり衣被からきてるんやろうな。
清水__植物は成長過程で細胞分裂するとどんどん縦に伸びるけれども、動物は表と裏がひっくり返るということを何度も繰り返すんですよね。何かそういうものなのかもしれないなと思って。
生まれたとき、胞衣の中にくるまれていたように、生まれてもまたそういうものを着せるんですよね。殯というものがあるじゃないですか。人が亡くなったのにいつまでも埋葬しないで曖昧にしておく時間があるけれども、その殯の逆のようでもありますね。
源兵衛__そうそうそう。
清水__そんな感じですね。生きているし生まれているんだけどはっきりしない。最近僕は仏教で《不生不滅》というのは、誕生や死の境界がはっきりしないということじゃないかと思っているんです。「誕生と死を直視すること」が神話でタブーになっているのもそのためなんじゃないか。生命とは時系列で縦にまっすぐ直線的に生き、ここから始まってここで終わる、というようなものではない。
西行の歌でもそうだけど、誰かの「現われ」というのは別の誰かのこころに対する「現われ」だし、そのこころも「現われ」もさまざまに変わったり、同じであったり……。そういう横の交錯がお互いに複雑にあって、そのなかで生きる無力さとか悲しみとか喜びがあって、そうやってできているのがわれわれの生で。《不生不滅》というのもただ引き延ばして生きているとか、そんなことではないと思うんです。
人間の文化というのは、何か次々時系列で新しいものが出てきて塗り変わっていくようなものではないし、遥か過去からのものがいまだに息づいている……。やっぱり西洋の文化だと、あまりギリシャを意識しなくなってきてから急激に色褪せてしまった。これが日本だったら色々あるだろうけどアニミズムとか、仏教から出てきた文化が……。
源兵衛__いや、もうその辺にしかないと思う。
清水__そうですよね。
源兵衛__もし何かをひっくり返す可能性があるとしたら、そこにしかあらへんのやないかと思うわ。
〈第7話|「いのちの被膜」をめぐる対話|了〉
|人に潜る|松井至|
|第1話|家は生きていく|石巻|①|②|③+映像|
|第2話|近くて遠い海へ|いわき|①|②|③+映像|
|第3話|人はなぜ踊るのか|川崎市登戸+映像|
|第4話|ゆびわのはなし|奈良|①|②|③+映像|
|第5話|いのちの被膜|京都|①|②|③+映像|
|第6話|握手|
|第7話|「いのちの被膜」をめぐる対話|京都|前編|中編|後編|
|第8話|田んぼに還る|西会津|①|②|③|④|⑤|⑥|⑦|⑧|
|第9話|光を読む|『私だけ聴こえる』|①|②|③|
|第10話|うたうかなた|前橋|①|②|③|④|
|最終話|想起するまなざし|
松井至[まついいたる]
1984年生まれ。人と世界と映像の関係を模索している。
耳の聴こえない親を持つ、聴こえる子どもたちが音のない世界と聴こえる世界のあいだで居場所を探す映画『私だけ聴こえる』が公開され、海外の映画祭や全国40館のミニシアターで上映され反響を呼んだ。令和4年度文化庁映画賞文化記録映画大賞受賞。
誰からでも依頼を受けるドキュメンタリーの個人商店〈いまを覚える〉を開店。
日本各地の職人と自然との交わりをアニミズム的に描いた〈職人シリーズ〉を展開。
コロナ禍をきっかけに、行動を促すメディア〈ドキュミーム〉を立ち上げる。
無名の人たちが知られざる物語を語る映像祭〈ドキュメメント〉を主催。
仕事の依頼などは 【こちら】まで。
松井至[まついいたる]
1984年生まれ。人と世界と映像の関係を模索している。
耳の聴こえない親を持つ、聴こえる子どもたちが音のない世界と聴こえる世界のあいだで居場所を探す映画『私だけ聴こえる』が公開され、海外の映画祭や全国40館のミニシアターで上映され反響を呼んだ。令和4年度文化庁映画賞文化記録映画大賞受賞。
誰からでも依頼を受けるドキュメンタリーの個人商店〈いまを覚える〉を開店。
日本各地の職人と自然との交わりをアニミズム的に描いた〈職人シリーズ〉を展開。
コロナ禍をきっかけに、行動を促すメディア〈ドキュミーム〉を立ち上げる。
無名の人たちが知られざる物語を語る映像祭〈ドキュメメント〉を主催。
仕事の依頼などは 【こちら】まで。
最新記事
- 松井至さん と
『つぎの民話』のこと2025年09月12日 - ソラノマド|高山なおみ
夏の縁側2025年08月26日 - 柳亭市若さん
葉月の落語会
「小桜」ほか2025年08月12日 - 夜のとしょかん、第33夜
漫画『とつこ』ができるまで2025年08月05日 - ソラノマド|高山なおみ
土用干しの庭2025年07月25日
アーカイブ
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年4月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年6月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年2月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2015年9月
- 2015年4月
- 2015年2月
- 2014年11月
- 2014年9月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2013年8月
- 2013年6月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月